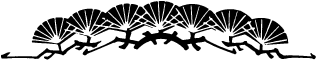
昔も今も。剣菱の“あるべき姿”
菰樽(こもだる)・樽(たる)
現在はお正月や結婚式、記念日など、お祝いの席を彩ることが多い樽酒(たるざけ)。“めでたいものの象徴”という印象が強いが、かつて(瓶が主流になる以前)の日本酒といえば樽酒であり、それが“当たり前の姿”だった。
昔も今も、樽の製造は手作業。杉材を用いて、職人がひとつひとつ丁寧につくり上げていく。なお、ひと言で「杉」といっても「白太(しらた)」「甲付(こうつき)」「順礼(じゅんれい)」「赤味(あかみ)」と、肉の部位のように部分ごとに名称が異なる。樽酒に一般的に使われるのは、「甲付」と「赤味」。「甲付」は1本の杉から少量しかとれないいわば“稀少部位”で、「赤味」に比べて木の上品な香りが酒に付きやすい。「赤味」はいわば“標準的な部位”で、「甲付」に比べて木の香りや色が酒に付きやすく、しっかりとした味わいになる。
そして、樽の外側を彩る菰(こも)。江戸時代、船で酒を運ぶ際に樽が壊れないよう巻いたのが始まりとされる菰は、時代の移り変わりとともに、藁(わら)からナイロンやポリエステルへとその姿を変えつつある。上質な藁が手に入りにくくなったことや、巻き付ける手間の軽減、さらに「藁くずが床に落ちる」といったお客さまからの要望がその理由だが、剣菱では今も藁を使い続けている。
「にわか雨 池田伊丹に 足がはえ」(にわか雨に遭った人が池田産や伊丹産の酒樽の菰をまとい、まるで菰に足がはえたような様子)、「剣菱の 大紋を着る にわか雨」(同じく、にわか雨に遭った人が剣菱の菰をまとった様子)とは、江戸時代の川柳。樽のなかの酒はもちろん、外側の菰まで含めて剣菱は多くの人々に愛され続けてきた。
“当たり前の姿”から“めでたいものの象徴”へ。時代とともに用途は変われど、剣菱の菰樽(こもだる)が多くの人々の新たな門出や、それに伴う喜びや決意など、お客さまの大切な思い出のワンシーンに寄り添っていることに違いはない。












